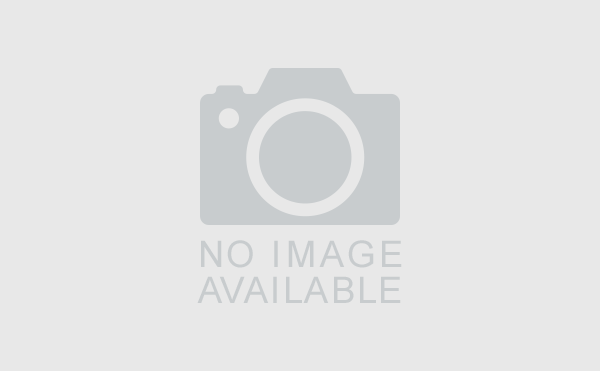複雑な感情を独特な美術表現で魅せる「モノノ怪」
「モノノ怪」のあらすじ
諸国を旅してまわる謎の薬売りが主人公。
あやかし(妖怪)があらわれる不思議な出来事が起こる場所に、この薬売りが現れ、彼が不思議な力を駆使しながら事件の真相を明らかにしていく。
そこでは人の恨み、憎しみ、嫉妬といった情念、怨念が絡んでおり、それがあやかしに取り憑くことで人に害をもたらす「モノノ怪」になってしまったことが明らかになる。
薬売りはそんなモノノ怪を斬ることができる不思議な刀を持っているが、その刀を振るうためにはモノノ怪の「形(かたち)」、「真(まこと)」「理(ことわり)」を明らかにする必要がある。
そのため薬売りは事件の関係者とさまざまな形で関わりながら真相へと切り込んでいくのだが…。
「モノノ怪」の登場人物と見どころ
一話完結のオムニバスの形を取っているため、シリーズを通して登場するキャラクターは薬売りのみ。
整った顔立ちをしているがどこか常人離れした不思議な雰囲気を身にまとった青年だ。
ほかには、複数のエピソードに登場する加世(かよ)などがおもな登場キャラクターとして挙げられるだろう。
それ以外は各話に登場するのみとなっている。
この一話完結のオムニバス形式になっているのが、この作品の見どころとして挙げられるだろう。
謎の薬売りが各地を旅してまわりながら遭遇する不思議な出来事を解決していく、時代劇のような体裁をとっているため、どの話から入っても楽しむことができる。
それから最大の見所となっているのが、和風ホラーであること。
それも舞台が現代ではなく、江戸時代を思わせる世界観となっており、ありそうでない「和風時代劇風ホラー」となっている。
しかも演出がユニークで、あえて紙芝居風を思わせる平坦なアニメーションになっている。
ちょっと浮世絵的な雰囲気を感じさせる一方で、クリムトやピカソといった西洋美術、さらには竹久夢二のような大正ロマンの世界観をも取り入れた、独自の世界を築き上げている。
あえて立体的な要素を控えて、しかもモノクロ的な雰囲気を取り入れることで和風の雰囲気をさらに強めると同時に、作品の世界観に奥行きをもたらすことに成功している。
この演出・美術面が、「モノノ怪」を他のホラー系&和風アニメと一味違うものにしているといってもいいだろう。
さらにストーリーもひと捻りしているうえに、人間の醜さ、業の深さを描き出す点を重視しているのも面白い。
「座敷わらし」や「海坊主」、「のっぺらぼう」といったおなじみの妖怪をタイトルにしているのだが、実際の内容はこれらの妖怪の一般的なイメージとはかなり異なる。
人間の怨念やエゴと結びつくことで、これらの妖怪がより恐ろしく、また哀しい存在として表現されているのだ。
妖怪と人間両方の怖さと哀しさを見事に表現されているとも言えそうだ。
見ていてぼく自身もこんな妖怪になりそうだ…なんて思っちゃったのは、ちょっとまずいのかな。
妖怪好きの子どもよりも、むしろ大人が見て深い感動を得ることができる、そんな作品として評価できるだろう。